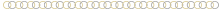
|
世紀末の美術館めぐり |
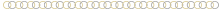 |
|
このページには、触ることにこだわって書いてきたものを集めてみた。 なんとぼくは、この90年代を、触ることにこだわって生きてきたのだろうと感心してしまう。 しかし、これらを読み返してみると、もう一つ明らかなことがある。 それは、ぼくが触ることにこだわってきたのと同じように、現代アートの動きも確実に触覚を含めた五感にシフトしてきたことだ。 最後に載せた『暗闇は透き通っていた』になるとそのことがハッキリとしてくる。 さらに、ぼく自身のことで言えば、言葉による対話型の美術鑑賞によって、新たな“観方”を切り開こうとしている。 昨年秋から始めた「ミュージアム・アクセス・ビュー」の活動がそれだ。 触ることを卒業したわけではないが、さらに美術に近づく方法として、美術館に、ギャラリーに、この新しい方法を持ち込もうとしているのである。 |
 |
|
■ イサム・ノグチの彫刻に触れてみて(美術館めぐり Part I.) ■ 手の中の虹(美術館めぐり Part II.) ■ やっと見つけた名古屋市美術館(美術館めぐり Part III.) ■ 最近触っておもしろかったもの ■ 光→徳通信第2信―――点字の世俗化 ■ 二つの展覧会 ■ 暗闇は透き通っていた |
 |
| ■イサム・ノグチの彫刻に触れてみて(美術館めぐり Part I.)■ |
|
ぼくは、美術作品を手で触って鑑賞するのが好きで、よく遠くまで足を運ぶ事がある。東京渋谷にあるギャラリーTOMでは、我々視覚障害者が触れて鑑賞できるものを集めて、いつも楽しい作品展を企画してくれる。又、兵庫県立近代美術館も、毎年この時期に、自由に触って鑑賞できる作品展を開催してくれている。 去る七月二日、京都国立近代美術館へ行って、イサム・ノグチの彫刻を触って鑑賞する機会を得た。友人から「イサム・ノグチの作品展なら、触っておもしろそうだ」と聞いて、早速美術館へ電話をかけて、触らせてもらえるかどうかを確認した。というのは、ぶらっと美術館へ出向き、触れそうな物に手を出そうとすると、すぐに係員の人がとんで来る。そして、 「壊れる心配があるので、ご遠慮下さい」 あるいは、 「危険ですから、触らないでください」 と言われてガッカリすることがよくある。 「じゃあ、眼の見えないぼくはどんなふうに鑑賞すればいいのですか?」といいたくなる。そこで、今回は事前に確認をとってから行こうと思ったのだ。「所蔵館の了解を得ている物に関しては、触ってもらえる」との返事だったので、ぼくは期待して出かけた。なにしろ、学芸員が付き添って説明してくれるというのだから、とても楽しみだった。 最初に、触ることが許された石の大きな作品を、三つ鑑賞した。大きな石の中から、水があふれて、流れていく作品はとてもおもしろかった。水の落ちる音、石の冷たさ、柔らかく流れる水の優しさは、安らぎを感じさせてくれた。又、地を這う風を表現した、細長くねじれた石の彫刻も、そのうねりかたが何とも言えず感動的だった。 続いて、触ることが許されなかった作品を、ひとつひとつ丁寧に学芸員に説明してもらった。これなら、全盲のぼくが一人で美術館へ来ても大丈夫なんだなあ、と感じた。ところが、その説明を聞いているうちにだんだんむなしくなってきた。途中で説明を中断してもらい、残りの時間は、触れるものだけをゆっくり鑑賞することにした。というのは、やはり説明には限界があり、説明がうまければうまい程、よけいにその作品を触ってみたくなるからだ。 結局、ふれることができたのは、石の作品が殆どで、全部で百点程のうちわずか九点だけだった。そのうえ九点の内、一つの作品は、手で直接ふれると手垢やあぶらがついて、汚れが取れにくい大理石とやらで、薄い手袋をさせられて鑑賞した。いくら薄いとはいえ、布の手袋をして点字を読むことができるだろうか? 薄い布で目隠しをして作品を見ろ! というようなものだ。でも、触れないよりは触れたほうがいい!! 怒りをぐっとこらえ、触らせてもらうことにした。 スーパーで、ラップされたトマトやナスビを触っているようなもので、その新鮮さや、その物自体の感触はなかなか伝わってこない。実に後味の悪い作品として、イメ−ジが残ってしまった。ブリキやブロンズなど、違った素材のものにもふれてみたかったのだが、それも許されなかった。 帰りがけに、美術館の人と少し話す機会を得て、次のようなことを要望した。 目の見えないぼくが作品を鑑賞するには、手で触るしか方法がない。予め作品を借り出す時に、視覚障害者が鑑賞することを前提にして、許可を取っておいてほしい。そうすれば、いつでも気楽に美術館へ行って、鑑賞できるのではないだろうか。又、ふれるということについて、「壊れる」という基準が、一般の人と我々視覚障害者では少し違う。我々は目で見る代わりに手でふれてものを理解する。例えばチューリップの花の場合、花びらや、めしべ、おしべなどを分解することなく、触って認識する。包丁やナイフも日常的に使うわけだし、よほど危険なものでないかぎり、けがをすることはない。そのあたりも充分考慮して、触れる作品かどうかを判断してほしい。 美術館を出てからふと気がついたのだが、入場料を払っていない。障害者の入館は、“無料”だったのかなあと、いまさらながら、“無料”の意味をかみしめた。たとえ入場料を払ってでも、触れればいい。触る権利を主張できにくいのは“無料”にしてもらっているからだろうか? 本当なら今、イサム・ノグチの作品に触れて、とても爽やかな気分になっているはずだが、実際は戦い終え疲れ果てた気分である。もう少し楽な気分で彫刻に触れたかった。 1992年8月22日(「楽点キーNO.1より」) |
| ■手の中の虹(美術館めぐり Part II.)■ |
|
8月のある暑い日、ぼくは兵庫県立近代美術館へ出かけた。「誰もが触って楽しめる」という企画で、もう4回目となるこの作品展には、前にも来たことがあるので、なんとなく安心してやってきた。なぜなら、「作品には、手を触れないでください!」という係員の声にびくびくしなくてもいいからだ。 受付には、点字のパンフレットと、連絡先や感想を書くための点字器が用意されていた。 「さあ、触ってやるぞ」といさんで時計をはずし、白杖を折りたたんで美術鑑賞の開始。ぼくが、気にいった『虹』という石の作品をゆっくり触っていると、小学生らしい団体がガヤガヤと入ってきた。 「さあ、みんな触って、触って」 という指導員らしい人の声にはあっけにとられてしまったが、暫くしてその中の2、3人がぼくに近寄って来て、子どもどうしでなにやらヒソヒソ話をしている。まもなく、 「なにしてんの?」 とぼくに問いかけた。 「見えへんから触ってるんや」 なんとか、そう応えてみた。子どもの素朴な質問には、即座に応えるのが難しいものだ。あっけにとられて、想いが言葉にならないうちに、その場面がすぎさってしまうこともよくある。わが子の質問責めに少しは慣れてきているので、こんな時もなんとか対処できるようになった。最近は、少し気もちの余裕というものができてきたらしい。さあ、次の質問はなんだ!!と待ちかまえていると、 「これ、なに書いたるの?」 と、作品名と作者が書いてある点字のプレートのことを聞いているらしい。 「これはねえ」 といいながら、指で読みすすむと、次は、「これは?」と、どうも墨字(点字に対して、一般に使用されている文字のこと)の文章を読めと言っているようだった。 「これは、おっちゃんには読めへん、そやろ」 と言うと、 「見えへんのかわいそうやなあ」 と返してきた。これはたいへん、見えないのが“かわいそう”なんて思われては、ぼくが“かわいそうな人間”になってしまうではないか、あわてた。なんとか、言葉を返さなくっちゃ。こんな時のマニュアルは、同じ言葉を繰り返せ!というのをなにかで聞いたことがある。 「そうか、見えへんのかわいそうかなあ?」 と、やっとその場をつくろって、なんとか先を続けようと思っているうちに、子ども達は、白い杖がどうとか、しゃべりながら遠ざかっていってしまった。こんな時にいつも思うのは、もう少し子ども達と納得いくまで、しゃべれたらということだ。でも、これはぼくの方だけが、そう思うので、案外子どもの側は、それだけの会話で満足しているのかもしれない。常にぼくの方には、心残りが渦巻いて、もっと伝えたいことがあった、と思い返すのである。少し残念な気もしたが、まあ、これこそ晴眼者とのふれあい、ぶつかり合いだなどと考えてみたりした。 ぼくは気をとりなおし、もう一度この『虹』をしっかり手の中におさめ、頭の中で形を再現できるまで触り続けた。冷たくて気もちいい、石で作られた虹の橋をたどっていくと、雨に出会い、さらに上へ手を伸ばすと、雲が手に触れる。 子どもの頃、みんなが「虹が出てる!」と言っているのを聞いて、虹の方向をいっしょうけんめい見ようとするのだが、なんとなく見えるような気もするけど、本当には見えていなかった。その時に見えなかった虹を、ぼくは手の中に包み込んで、ほっとした気分になって美術館を後にした。 1992年12月1日(「楽点キーNO.2」より) |
| ■やっと見つけた名古屋市美術館(美術館めぐり Part III.)■ |
|
昨年9月、ぼくは友人(晴眼者)と、名古屋市美術館へ出かけた。「セブン・アーティスツ ―― 手で見る美術展」と題して、一般の人にも触ってもらおうという企画だった。 高速バスで約3時間、地下鉄に乗り換えやっとたどりついたと思ったら、それは県立美術館。目当ては市の美術館なので、また一駅戻り、約10分歩いて到着、やや疲れた足取りで受付を通り過ぎようとすると、 「杖を預かりましょうか?」 といわれた。少し様子がおかしいと思い、おそるおそる 「触れる作品展でしたね?」 と尋ねた。 「申し訳ありませんが、触れるのは地下1階だけです。」 と言われてがっかり。 これはまた、イサム・ノグチの繰り返しかと滅入った気分になり、さっき言われた杖のことが頭に蘇ってきて腹が立ってきた。杖は凶器だとでも思っているのか! それとも、鑑賞の邪魔になると思っての親切なのか、よく解らないが、とにかく杖はぼくにとって、人に預けてしまえる物ではない。肌身離さず持っておきたい。なれている家の中などでは確かに邪魔になることもあるが、なれない所ではこれが頼 り。もし、手引きの人とはぐれても、この杖さえあれば何とでもなると自信を持っている。 まあ今は、杖のことはいい。この触れないフロアはざっと友人に説明してもらい、地下へ降りた。 さて、そこには点字のパンフレット、手引きのボランティアと、サービスが行き届いていてびっくり。 上の階とはなんという違いなんだろう。二つ三つ触っていると、 「この作品は触っていてどんな感じがしますか?」 と声をかけてきた女性がいた。喋っているうちにこの作品展を企画した学芸員だということがわかった。 作者の意図や、作品の構成などを詳しく説明してもらいながら鑑賞を続けた。 ぼくが気に入った作品は、ボーンチャイナでできた『木の肉・土の葉』という作品だった。薄い焼き物で作られており、ひとつひとつの大きさは両手で包み込んでしまえるほどの物だった。それらが約70ほどもあっただろうか。ずらりと円形に並べられていて、それぞれ少しずつ曲線や薄さが違っている。ひとつずつ触っていくには時間がかかったが、指先とボーンチャイナが擦れ合う微妙な音も魅力で、次々触っていった。 残念ながら、床に置かれたこれらの作品をしゃがみこんで鑑賞するのは少し疲れた。視覚的にはこの配置がいいのかもしれないが、触る者の立場からすると、テーブルぐらいの高さの台の上に並べられていた方が苦痛なく鑑賞できたと思う。見ればひと目で分かるのだろうが、我々の場合順々に見ていって最後に全体を頭の中で描きなおす。だからひとつの作品を見たというより、70余りの作品を鑑賞し終わった感じだった。 結局、ぼくにはこの作品の全体像を掴むことはできなかった。それぞれの形の違いを楽しんだわけだ。 見える人はこれらの作品にいったいどんな美を感じるのだろう?逆に触っていて美しい形とはどんなものだろう。そのあたりが学芸員にも興味があるらしくそんな話題で話がはずんだ。こんなにザックバランに話ができ、障害者にも自らの視線を向けようとする学芸員が、もっと沢山いれば美術館も我々にとって身近なものになるだろう。 今回の企画では、美術館ツアーとして地域の視覚障害者も沢山招待されていたようだ。ある全盲の女性は、この作品を触って「ケーキの上に飾りつけられるチョコレートの薄片みたいでおもしろい」という感想を残したらしい。あいにくぼくは、ケーキ作りをしたこともなく、出されたケーキをゆっくり触ってから食べるという習慣もない。食べながら、ついでに舌や唇で形や歯ごたえを楽しむくらいなので、この感想にはピンとこなかったが……。 入館したときの受付でのインフォメーションでは、上の階の作品には触れないと聞いていた。しかし、学芸員の付き添いがあれば、それらの作品にも触らせてもらえることが分かった。触ることが可能なものについては全て心おきなく鑑賞させてもらった。やっと見つけた楽しめる美術館だった。 他にも面白い作品が沢山あったが、それらを全部紹介できないのが残念だ。2時間余り楽しい時間を過ごしたあと、ラウンジでコーヒーとチョコレートケーキを食べながら、友人と感想を話し合った。しかし、その時にはもう先程の薄片の飾り付けのことはすっかり忘れ、まずは、むしゃむしゃ食べ始めてしまっていたのだった。 帰りに、中庭にあるイサム・ノグチの背よりも高い作品を思う存分触った。やや埃にまみれてはいても、やはりイサム・ノグチの繊細さはぼくを楽しませてくれた。 3回にわたって「美術館巡り」の文章を書いてきたが、ここで書いた作品の感想は勿論ぼく個人の感じ方であって、視覚障害者一般の意見ではない。よくそんなふうに誤解されることがあるので、思い切った発言がしにくいことがある。感じ方は人それぞれ。ぼくは目がみえないわけだが、(見えない)というところでくくらず、光島貴之の感想として読んでいただきたい。 1993年3月10日(「楽点キーNO.3」より) |
| ■最近触っておもしろかったもの■ |
|
この半年あまりの間に、ぼくが触っておもしろかったものを独断と偏見で評価しながら紹介します。 5段階評価で、Aが一番すばらしい、Eがもっとも最悪というふうにです。これはぼくの好みの問題です。障害者にたいして、福祉的に行われる厚意や、政策は不平をいわずにありがたく受け取るのが、当り前になっていますが、障害者も好き嫌いでものを言ってもいいのではないでしょうか?わがままだと言われても、その方がずっと人間らしい楽しい生活が送れるでしょう。 1 西村公朝作「ふれあい観音」 評価/E。 これは最悪。ある集会で「ふれあい観音」を触らせてくれると言うので、いい機会だと思って出かけた。テレビなどでも紹介されていたのでご存知の人もあるかもしれない。ぼくの感想は、唇の形がやや四角っぽくて、ふくよかな顔とは相容れないこと、素材がプラスチックであることが気に入らなかった。いかにも触らせてあげましょう、救ってあげましょうという印象だった。同席した人の話では金ぴかに色づけされているとのこと。 以前、長谷寺の宝物館で特別に頼み込んで触らせて貰ったほっそりした木彫となんという違いだろう。 やや湿りっぽい空間の中でひんやりと静かに存在していたあの観音像のことが今でも最高のイメージでぼくの中に残っている。作者には非常に申し訳ないが、偽物を触ったような気がした。仏像彫刻は直接寺にいって本物を触るのが一番。 2 御堂筋(淀屋橋と本町の間に最近設置された三つの彫刻)で見たボテロの『踊り子』評価/B。 これはびっくり、人の形だろうと思いながら触ったが足なのか胴体なのか、もう一つの足はどうなっているのか、肉付きの良すぎる形はぼくには美しいとは思えなかったが、その迫力は絶品。グロテスクとしかいえないが今でも印象に残っている。800人ほどの患者さんを治療してきたが、こんな身体には触れたことがない。 3 同じく御堂筋、佐藤忠良の『レイ』 評価/B。 少し肉付きのいい裸婦。手を後ろにまわしていることもあるのだが、その肩のラインは肩凝りを思わせた。日常的に肩凝りの治療をしているからか、そのあたりが気になった。ぼくがもしこれから作品を作るとしたら、「肩の凝った人」というテーマだなあと思った。 4 ある会合で出口を教えて貰う時、手を引っ張ってくれた人の手 評価/A。 ほんの2、3秒触れた手だが、なんとも繊細で優しかった。暖かくて滑らかでほっそりしていた。この手の印象だけが脳裏に焼き付いてしまったのだがそれが誰の手だったのか、なかなか思い出せずに困っていた。でもやっと思い出しました。しかし、それは内緒。 5 江部診療所の待合室にある丸テーブル 評価/A。 漢方薬を 処方してもらうのに何度か来院しているが、そこの看護婦さんが待合室を模様替えしたこと、そしてテーブルを新しくしたことを説明して触らせてくれた。別に治療とはなんのかかわりもないことだが、このちょっとした気遣いがなんとも嬉しい。そして、触ったテーブルもなかなか趣味良し。じつはそんなふうに言ってもらわないと見知らぬ所で家具をゆっくり触るのは恥ずかしくて後込みしてしまうものだ。ぼくが何の用事もないのにテーブルをごそごそ触っている姿を思い浮かべると手がすくんでしまうのである。 御堂筋の路上で、ぼくが「裸婦」をゆっくり触っている姿を想像してみてください。触るということにはなにか猥褻なイメージがついてまわるのか、「触らせてほしい」と主張するにはちょっと勇気がいるものだ。 5 人の顔 評価/C。 ある集会の帰り、飲み屋さんで触った10人以上の顔。ぼくの書いた「美術館巡り」の話から、参加者の顔を順番に触らせてもらった。 この人は美人だとか、ちょっと金丸に似ているとか、いろいろ説明してもらいながら触ったが、実際、ぼくにはよく解らなかった。というのは、彫刻のようにスタティックな物ではない本物の顔はよく理解できない。それに普段治療で触っているのは身体がほとんどで、顔をゆっくり触るなどということは我が子を除いて今まで経験がない。何を規準に美人だとか、ハンサムだとかいうのか、ピンとこなかった。もっとたくさんの顔を触っているうちに、その顔の特徴やイメージを作れるようになるのかなあ。 今度お会いしたあなたの顔も触らせてもらいますよ。 1993年6月11日(「楽点キーNO.4」より) |
| ■光→徳通信第2信―――点字の世俗化■ |
|
9月1日の日曜日、兵庫県立近代美術館へ行ってきました。昨年は、震災の影響で中止されたのですが、毎年夏に行われる「美術の中の形―――手で見る造形」です。 今回は、千葉盲学校の生徒の作品群と、オット氏の「変心装置」、そして、美術館所蔵のロダンやマイヨールの作品などです。それらは、それぞれ別々にまとめられて配置されていたのですが、手引きをしてくれた人が二日酔いだったせいもあって、壁沿いにグルグル回ったので、ロダンもマイヨールも千葉盲の作品もごちゃ混ぜに触っていったわけです。すると、千葉盲の作品のいくつかはロダンのそれよりずっとすばらしいと感じました。もちろん、タイトルや作者は点字でも表記されてますから、ぼくの頭が混乱していたわけではありません。 あえていうなら、ぼく自身作品そのもののすばらしさを感じとれるようになってきたんだなあ、と喜んだのです。盲学校の生徒の作品というと、晴眼者がそれを見るのとは違った意味でぼくも偏見を持っていたのです。晴眼者の場合、 「目が見えないのに何でこんなすばらしいものができるの!」といった感じでしょう。ぼくの場合は 「どうせ盲学校の作品や。そんな大したことない。何やかんや言っても所詮一般のレベルには追いつけへん」、なんて思っていたのです。そうした先入観を持たずに、作品そのもののすばらしさを味わえるようになってきたんだと思います。 「変心装置」は、185センチ四方の暗室にいろんなもの(おっぱいやペニスなど)が並べられているものでした。現代アートは、観客がものの感じ方を変化させるための装置だと言うのがオット氏の主張です。見る側の意識変革を助けるものとして、自らの作品を位置づけているようです。 だからでしょうか、見えないぼくにはあまりおもしろさが伝わってきませんでした。パリで行われたという「闇の中の対話」という作品は、美術館全体を暗室にして、その中にいろんなものが配置され、そこを視覚障害者がガイドとなって晴眼者を案内するというものだそうです。見終わったあとでそうした体験を話し合う酒場のようなところも用意されているそうです。従って、お互いの関係性を明らかにしようとするものでもあるのでしょう。 今回のオット氏の作品では、視覚障害者の観客は意識されていなかったように思うのです。以前に見た、嶋本昭三氏の「視覚障害者のためのアート試作」というのは、足裏の感覚で世界を認知しようという作品でしたが、晴眼者が見えない世界を味わう、かいま見るという感じで、ぼくには物足りない作品でした。 今年の2月だったか、あなたと一緒に行った心斎橋のキリンプラザでの石原友明氏の「美術館で盲人が透明人間に出会ったとせよ」は、どんな印象でしたか? 点字が床に敷き詰められ、その上を裸足で歩いてみるというものでしたね。ぼくにとっては、ある種神聖化された文字に対する揺すぶりを感じました。 点字はボランティアが“心を込めて”打ってくれる神聖なものである。たとえ必要性がなくなったとしても、そう簡単にごみ箱へ捨てることのできないものとして、ぼくは無意識の呪縛を受けていました。 思い出すのは、もう20年も前のことになってしまいましたが、大学での教科書点訳のことです。当時は、点訳サークルの協力によって初めて講読などの講義に参加できるといった状態でした。一度英語の教科書点訳をめぐって、こんなことがありました。みんなで分担して、何とかその講義の時間までに点訳してくれたのですが、ぼくはその講義をサボってしまったんです。みんな遅くまでサークルのボックスに残って点訳してくれたのですから、みんなの憤りはただならぬものがありました。 「大事な時間を割いて点訳しているのだからそれを踏みにじるようなことをしてはいけない」 「我々は、点訳機械ではない。真心を裏切るようなことはするな!」 というようなことを言われました。 ぼくも人間や。いつもいつもまじめではいられない。たまに講義をサボって何が悪い(本当はたまにではなかったが)。でもそのときのことは、今でも罪悪感をともなって思い出すことがあります。 最近では、パソコン点訳が急速に一般化し、真心コミュニケーションの手段としての点字ではなく、文字情報としての点字があたりまえにはなってきましたが、それを足で踏みつけるのですから、変な感じです。そして、足裏では文字として認識できないのは晴眼者も視覚障害者も同じです。 あとから聞いたところでは、その金属板に打ち出された点字は、作家自身が一つ一つ穴を開け、ピンを打ち込んだのだと知りました。さらに、キリンプラザの外壁には、点字が型どられ、暗くなるとライトアップされていましたね。手の届きそうもない高いところにならべられたそれらの文字はぼくには永遠に認知できないものであり、一方、晴眼者でも点字を知らない人には意味を持たないものでしょう。こうした晴眼者と視覚障害者のすれ違いながらの行き来は、まさに彼が意図したところの“交通と反交通”をみごとに表現していると思います。 重要なのは、健常者も障害者もお互いがそれぞれの場面で、主人公になりうる仕組みを作ることではないでしょうか。つまり、オット氏や嶋本昭三氏の作品ではぼくは日常を追体験するだけです。ところが、石原友明氏やたぶん「闇の中の対話」でもそうだと思いますが、ぼくはぼくなりに点字に対する価値観を揺さぶられるという非日常的な体験をする事ができました。 1996年10月1日 *この文章は、徳岡輝信さんとの往復書簡として『教育解放』27号(1997年3月発行)に掲載していただいたものですが、今回このページにアップするに当たって加筆訂正して部分的に掲載させていただくことにしました。 前文をお読みになりたい方は、 http://www.nanbook.com/ffe でどうぞ。 |
| ■二つの展覧会■ |
|
憤りを感じる度になにがしかの文章を書いてきたぼくだが、最近は書くのを忘れている。年をとって怒りもどこかへ失せたのか、それとも、幸福過ぎる人生を送っているのか? と考え込んでしまった。 そんな10月のある日、文化博物館で行われていた「アールブリュット ―― 生の芸術」に出かけようと、いつものように問い合わせの電話をした。 「視覚障害者なんですけど……」 「身障者手帳はお持ちですね」 「ハイ」 「でしたら、入館料は無料ですので」 「イエ! そうじゃなくて、作品を触らせてもらいたいのでお聞きしてるんです」 「ああ、そうですね。ちょっとお待ちください」 暫く電話口で待たされて、結局、触るのは無理だという返事が返ってきた。いくら無料にしてもらっても触らせてもらわなければ意味がない、と抗議したら、係員ではこれ以上答られないから、実行委員会に直接電話するように言われた。今回の企画の趣旨は、障害者の作品を“障害者芸術”という枠に閉じこめるのではなく、一般のアートとして位置づけて、そのような見せ方をしたいというのが主催者のねらいらしかった。 「じゃあ、普通の展覧会の基準を当てはめたいから、同じようにしたいから、触ってはいけないということですか?」 と皮肉を言ってイラダツ気持ちを鎮めようとしたが、ますます怒りがこみ上げてきた。たぶん実行委では、障害者が鑑賞するなど考えてもいなかったのだろう。やっぱり京都はダメやなあ! 電話口からは、壊れやすいとか、解説できるメンバーがいないとか、断る理由が聞こえてくる。やっぱり世の中そんなに変わってはいない、と悪い方ばかり考える。それでも、ここで引き下がってはダメだ。気を取り直して、 「絵は説明してほしい。土の作品は作者の許可を得て、一つでも多く触らせてほしい」 と、要望して、やっと「考えてみましょう」という答えを引き出した。 絵は文化博物館の学芸員が説明してくれたし、土の作品にも触れたので、全体の雰囲気は何とか理解できた。もし、最初の電話で引き下がってしまえばそれで終わり。作品に出会う機会はなかっただろう。眼の見えない人は、美術には縁がないと思われがちだが、実際に興味を持っている人は多い。門前払いせずに、どうしたら鑑賞できるかを考えてほしい。 博物館から帰ってからも割り切れない思いをくすぶらせながら、どこかでこんな変なことがあったなあ、と記憶の糸をたどってみた。自然食品関係の店主と話していた時だ。 「ぼくも興味があるので、商品のチラシがあれば、ワープロうちしたものをフロッピーでいただけませんか。そうしたら、ぼくのパソコンがしゃべってくれます」 と言うと、その人は 「いやあ、そういう近代兵器は持ってないので……」と軽くいなされた。 その言葉の裏には、エコロジストであろうその人の文明批判が込められているのだろうが、どこか違う。たしかに、モデルチェンジをくり返しながら、より早いパソコンを売り出して、古い機種は使えなくしていくやり方には反発を感じるが、パソコンの普及で今まで享受できなかった文化を手に入れようとしている障害者に対して、そんな突き放した言い方はない。アートとして普通の見せ方をしたいと言いながら、視覚障害者の鑑賞を拒否する論理と、文明批判をしながら実は障害者の社会参加を妨げようとするのはどこか似ている。一つのことに熱心になるのはいいが、もう一つの意見を受けとめるバランス感覚だけは失ってほしくない。 次はぼくを幸せな気分にしてくれた展覧会を紹介する。 それは、8月に都の美術館で行われた「エイブルアート ―― 魂の対話展」だ。会場にはいると、MD(ミニディスクプレーヤー)を手渡されて、使い方を教えてくれた。館内の順路や絵の解説が録音されていた。点字の案内図もあったし、絵画を立体コピーなどで視覚障害者にも分かるようにしようという試みもあった。 当日販売していた一般向けの図録にも、手で触って分かるものが4枚含まれていて、みんなで一緒に楽しめるようになっていた。粘土の作品には触れたし、触覚をテーマにした作品もあった。これなら一人でぶらっとやって来ても疎外感を感じることはなさそうだ。 これらの二つの展覧会には、障害を持っている作家という視点からだけでは見てほしくないすばらしい作品がたくさんあった。一方で違いを感じたのは、観覧しようとする障害者に対する主催者の態度だ。見に来る人の中にも障害者がいることを忘れてはならない。どんな障害を持っていても、作品を見たい気持ちを妨げることは誰にもできないはずだ。あらゆる手段を駆使して作品理解を助けるのが学芸員の仕事であり、主催者に目指してほしい方向だ。 1997年11月20日 |
| ■暗闇は透き通っていた■ ■Dialog in the Dark KOBE 2000 −まっくらな中での対話−■ |
|
5月4日、神戸のポートアイランドにあるジーベックホールで行われていた「まっくらな中での対話」に、息子の瀬音と二人で行った。受付で予約番号を告げて、時間まで待った。受付の雰囲気も、さすがに入場料3000円を裏切らないものだった。 間もなく事務局の金井さんがやってきて、僕の杖に蛍光塗料などが付いていないかどうか、調べたいとの申し出があった。参加者には、それぞれアサガオのツルを巻き付けるための支柱が、杖代わりとして1本ずつ貸し出されることになっていたので、僕ももちろん同じものを持って入ることにした。ストラップも付いていて、軽くてスマートにできあがっていた。 いっしょに入場するのは、僕たち二人と後は若い女性3人だった。5、6人を一つのユニットにして、視覚障害者の案内役を一人付けるようになっているので、30分置きに一組ずつ入場している。入口で案内役の人が紹介される。入場者もそれぞれ自己紹介をしてから、杖の使い方などちょっとした説明を受ける。 そして、いよいよまっくらな中に入って行く。初めの設定は、橋を渡って森に入っていくというものだ。ガイドの人の声を目印にして、幅60センチぐらいの橋を渡る。 「落ちたらずぶぬれですよ」 とおどかされて、みんな杖で足元を探りながら、キャッキャッいいながら渡って行く。瀬音はまだなれなくて、僕にしっかりつかまっている。杖で調べたら、水なんかなくて、ビニールシートのようなものがしいてあった。 森は実際に木が生えていたり、倒れていたり、枯れ葉がしいてあったり、土もちゃんとあった。おもしろい仕掛けとしては、糸電話が空中にぶら下がっていて、歩いていくと顔にぶつかるようになっている。 それぞれ参加者が、誰かと通信できるようにしてあるようだった。またある場所では、大きな声を出すとこだまではなく、声が遠くまで吸い取られていく感じを味わえるように仕組まれているようだったが、それはいまいち成功していなかった。 森を出ると街だ。今度は、横断歩道を渡る体験である。実際に車が走ってくる音がする中を渡る。クラクションをならされたりしながら、あわてて渡って行く。僕は、わざとコースをずれてみた。すると、なんと本物の車がおいてあってぶつかるようになっていた。 次は、ヨットハーバーだ。桟橋の少し揺れる感じ、波の音、船が近づいて来る音などなど、なかなかリアルだった。スピーカーだけでも50台使っているそうで、金はかなりかけているようだ。部屋の反響を防ぐためにも、いろいろ工夫している。僕はみんなから少し外れていろいろ探検してみたが、ござを鉄柵に掛けて反響を少なくしているのを見つけた。 最後に設定されていたのは、公園である。千葉盲学校の生徒の粘土の作品が二つと、木琴・太鼓など楽器がいくつか列べられていた。そして、腰掛けて乗る二人用のブランコを体験して公園を出る。暗闇の中でのブランコはなかなか恐いようだ。気分が悪くなるという人もいた。この公園でアートに接するというところが、ちょっと弱いようだ。ここに触覚連画を登場させたいのだろうなあと思った。(以前に事務局の人が触覚連画に興味を示し、何かいっしょにできないだろうかという提案があった) そうそう、プログラムはまだ最後ではなかった。いよいよお楽しみの暗闇のバーである。飲み物はワイン・ビール・オレンジジュース・ウーロン茶が用意されていて、それぞれ好みの物を注文する。バーテンダーも視覚障害者だ。そのバーテンダー、どこかで聞いた声だと思っていたら、神戸大学に通うYという学生だった。実は、彼とはずいぶん前からのつきあいで、彼が小学校に入る前から点字などを教えたりしていた事もある。最近は僕の展覧会にも来てくれている。学芸員の資格を取ろうとしているらしい。思わぬところで出会ってお互いビックリ! バーでは、お互いの感想などを話すようになっていたが、ビールをもう一杯という雰囲気ではなかったのが残念だった。お酒を注文した人の感想では、暗闇の方が酔いが回りやすいと言っていた。 バーを出ると少し明るくした部屋に出る。そこには、スケッチブックが用意されていて、それぞれ思い思いの絵を描くようになっていた。その部屋担当の人も配置されている。少し心理学でも勉強しているような人が担当しているのではないだろうか。そんな感じだった。いきなり明るい世界に出ると、ちょっととまどう人もいるとかで、絵を描きながら見える世界への復帰を準備するようになっていた。 さて、瀬音の感想は、「いつものよりもおもしろかった!」だった。“いつもの”とは、僕の作品のことだ。 見える人にとってまっくらというのは本当にたいへんなことなんですね。瀬音は、バーで椅子に座るのさえ苦労していた。歩くよりもかえって目的の椅子に腰を掛けるという動作の方が難しいようだ。 「そんなにまっくらやったか?」 と聞くと 「ほんまにまっくらやで!! なんにも見えへんで。うす明かりでも少しあったら何とかなるけど」 と言っていた。 僕は、暗闇に付いての記憶をたどってみたが、本当の暗闇の記憶がない。中途半端な見え方しかしていなかったので、まっくらという記憶がないのだろうか? 少年時代を過ごした家には、裏庭があった。子どもにとってはかなり広い庭に思えていた。夜、そっとその庭に出てみても、僕には昼間の庭に関する身体感覚が染み着いていて、暗闇の中で、庭がぼんやりと浮かび上がるのだった。この感覚は、見えている人でも同じだろうか? しかし僕の場合、始めての暗闇であっても、子どもの頃から身に付けていた対物知覚のおかげて、何かがあることはすぐに察知できた。 だから真の暗闇体験がないのかもしれない。 今回体験したジーベックホールでも、暗いという感覚はぜんぜんなかった。天井はかなり高そうだけれども、音の反響はなく、スッキリとすみきった感じ。すべてのものがクリアに感じられる空間だった。見える人がおしえてくれる“一片の雲もない青空”とは、こんな感じだろうか。そのあおぞらの下で自由に動きまわっているように感じられたのは、周りに自由を失った人々がいたからそう感じたのだろうか。僕自身は日常と変わりないのだが、相対的にみて僕は自由になっていた。 僕はこのプログラム、アートの作品に触るのが目的だと思っていたが、実際には、街空間を擬似的に作り出してそこを視覚以外の感覚を動員して体験していくというものだった。決まったかたちがあるわけではなく、そのときどき、会場に合わせてさまざまな設定が行われているようだった。 この疑似空間、見える人にとっては二度と見られない街を体験したということになりますね。でもこれはアートと呼ぶにふさわしいのか? どちらかというと、ワークショップではないだろうか。見える人にかなりのインパクトを与えているのは確かですね。 *この企画は見える人をお客さんにして、視覚障害者が見えない世界を案内するという、今の社会構造を逆転した関係が成り立っているところがおもしろい。言うなら、僕は同業者である。同業者がお客さんとしてまぎれこんだのは、ガイドしている人にはずいぶんやりにくかっただろう。このプログラムを本当に楽しんだのは、見える世界に住む人々だ。しかし、僕もそれなりにかなり楽しませていただいた。その事を明らかにしようとしてこのレポートができあがった。 2000年5月31日 |