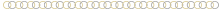
| ワークショップ編 |
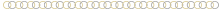 |
|
■ 日比野克彦のワークショップ ■ 阿部こずえさんとの往復書簡その2・ワークショップ編 ■ ワークショップ参考資料 |
| 「日比野克彦のワークショップ」 この文章は、MARのウェブサイトの「ミニエッセイ〜視覚障害者の視点〜」というページで紹介してもらっていたものです。 今回、ワークショップ関連のエッセイを一まとめにしたかったので、ぼくのページで も紹介させてもらうことにしました。 |
|
去る10月9日、日比野克彦を招いてミューズカンパニーのワークショップが、新
大久保の東京グローブ座・Aスタジオで行われた。 会場に入ってみると、あちらからもこちらからも知り合いの声が聞こえてきて、同窓会のような雰囲気でもあった。おそらく、30人以上の参加者があったのだろう。 その内、視覚障害者が7、8人。しかも年齢層は、10才ぐらいからかなりの年輩までさまざまだった。美術系のワークショップで、これだけの視覚障害者を集められる企画はあまりなかったように思う。それだけ美術と視覚障害者との間にはまだまだ隔たりがある。 僕は直前まで、参加するかどうかを迷っていた。なぜかというと、日比野さんには2年前、兵庫県立近代美術館で行われた展覧会「アート・ナウ98'―――アウトサイダー・アートの断面」で出会っている。そのときの関連イベントとして行われたトーク ショーは、すずかけ共同作業所でアートボランティアをしておられる、絵本作家のはたよしこさんと日比野克彦さんとの対談だった。その会場で、僕が質問をさせていただいたいきさつがある。 当時、なにを質問したのか? 明確には憶えていない。たしか彼は、知的障害の人たちとのコラボレーションに付いて話していた。でも僕は、彼と、知的障害者との間に距離感があるのを感じとっていた。アートという同じ土俵に上がりながら、対等な関係だといいながら、実際には隔たりが存在しているのではないか!? そのあたりのことを質問させていただいたと思う。 「アート・ナウ」には、僕も作品を出品していた。そんなこともあって、「この問題に付いては、作品で勝負するしかない!」という答えをいただいた。けっこう生意気で、いけ好かないやつだと思ったが、障害者におもねることなく、自分のアーティストとしての立場から、ハッキリものを言う人だという点は高く評価したいと思った。 それ以来僕は、きっとその内にもう一度「日比野克彦の前に作品を持って現れなければならない!」と思い始めた。 それからもう2年もたっているのだが、今回のワークショップのことを聞いたとき、 その時期はまだ熟してはいないだろうと思ったりして考え込んだ次第だ。 超多忙な有名人がそんな一言を憶えているはずもないし、(事実そうだったのだが) 結局あまり深く考えないことにして、チャンスは生かそうと思って参加することにした。 日比野さんの印象は、以前とかなり違っていた。トークショーのときは、ご自身の展覧会前でかなりイライラされていたように思う。今回は休日の雨ということもあったのか、ずいぶんゆったりした気分で話が進んでいった。最後まで、テンションが上がることはなかった。視覚障害者をたくさん前にして、ちょっととまどわれていたのかもしれない。 まず彼は、視覚障害者の参加者数人から、 「どんな風に見えているのか? それともぜんぜん見えていないのか?」 「夢の中に色が出てくるか?」 「いつ頃見えなくなって、色をどんな風に認識しているのか?」 などの疑問をインタビュー形式で聞き始めた。 しかし、失明時期もそれぞれ違うし、色に対する捉え方もそれぞれ違う。一般的には扱えないのだということが分かったところで、やっとワークショップが始まった。 最初は、口腔内のイメージを紙粘土で作るという課題だ。自分の口の中を、その場で見ることのできる人は誰もいない。舌でさぐるしかない。見える人も見えない人も同じ条件だ。後はいかに想像力を働かせるかだ!!というのがこの試みの意図らしい。どこかのコマーシャルで見たようなポリデントの入れ歯を作るのはダメだということで、みんな悩みながら作った。参加者全員の作品を触る時間はなくて、同じテーブルに居合わせた4人で作品を回して鑑賞した。 僕の作ったのは、『ある日、歯医者さんから帰ってきて』というタイトルで、麻酔が掛けられて、口の半分が感覚的には失われている状態を作った。そして、抜かれてしまった、蝕まれた大きな奥歯を横に添えた。 僕の向いに座っていた中尾さんは、はてしなく続く洞窟のイメージを口の中の感じと 重ね合わせていたようだ。湿り気も持たせて中もつややかに仕上げられていた。僕の作品とは正反対でロマンチックな作品だった。 午後からの課題は、新聞紙やダンボール、いろんな手触りの紙を使っての作品づくりとなった。ただそれらを使って何か作りなさいというのではない。まず、自分が今仲良くしている人たちを名字ではなく、名前か相性で10人書く。次に幼年時代、仲良くしていた人の名前を書く。そして、その中でもっとも古い記憶にある友達を思い出しながら、先ほどの材料で作品を作るのである。 僕の記憶をさかのぼってたどり着く名前は、「みほちゃん」だ。幼稚園のときに近所に住んでいた女の子で、間もなく引越していった。当時の視力では、みほちゃんの姿を遠くから見えるはずはない。近寄ってしゃべった記憶もない。でもなぜか気になる存在だった。 僕は、暫く考えた後、いつもの悪い癖で、勢いにまかせて何か手触りのおもしろい立体を作ってやろうと新聞紙を丸め始めた。 これらの記憶をさかのぼって作った立体作品も、ワークショップの時間内にはゆっくり触る時間がなかったので、終了後、どんな作品ができているのか中尾さんに案内してもらいながら見て回った。大まかには、四角い紙の上に箱庭式に作られたものと、僕の作品のように立体的に制作されたものに別れていたように思う。 それぞれ特徴のある個性的な作品ができあがっていた。指導者の影響を受けた、日比野克彦らしい作品群にはなっていなかったところがおもしろいし、そのあたりが大したものだ。このあたりが講師の力量の現れだろう。 プログラムはこれだけではなかった。これで終わったのでは、どこにでもあるワークショップに毛の生えたようなものだ。 僕たちが廃材で作業をしている間に何やら絵の具の匂いがしてくると思ったら、7、 8メートルほどの壁に真っ白な紙が貼られ、そこに絵をみんなで描くという作業が待っていた。そしてその壁の前には、手前に午前中から作った口腔内の紙粘土の作品が列べられた。その奥の壁際の方には、先ほど作った、もっとも古い記憶に残る人の名前から作り上げられた作品群がランダムに列べられた。その間を壁に向かっての通路が作られ、一人ずつ前に進み出て、好みの色で壁にペイントするのだ。 このような情景を中尾さんに説明してもらいながら、僕の頭の中ではミヒャエル・エンデの『モモ』に出てくる一場面にこんなのなかったかなあと想像をめぐらしていた。記憶をさかのぼり、過去の世界に踏み込んで、それから、“いま”の自分とはもっとも離れた遠い世界に入っていく。そこは、障害者であろうがなかろうが、誰もが持っている想像の世界だと彼は言いたげだった。 何かものを作り始めたとき、あるいは、想像をめぐらすとき、僕たちは、現実の世界から遠く離れていく。そのような体験は誰にでもあると思う。アーティストはその現実世界ともう一つの想像の世界との間に存在する壁を簡単に乗り越えられる人たちではないだろうか。もう一つの世界にいったまま帰ってこない人たちもいる。そのような人たちが知的障害者と呼ばれたりする。 ワークショップで作家が伝えたいものはそれぞれ違う。僕が参加して得たいものは、 技術や技ではない。作家の制作の原点をかいま見たいのだ。彼は、あの想像の世界で遊ぶおもしろさを、参加者に伝えたかったのだろう。〉 まず、日比野さんが、左端と、中央より少し左寄りと、そして右上にきっかけとなる絵を描いた。左下は、緑でストレートなキュウリを10本ほど。まん中には黄色で、鍵穴のようなかたち。右上は、十文字を赤で描いた。 最初は視覚障害者を含む10人ぐらいが、促されるままに一人ずつ前に進み出て、順に描いていった。壁に描かれて行くままを、日比野さんがスキャニングするように言葉にしていくのだが、抽象的なものを言葉にしていくのはかなりたいへんな作業だ。説明する人の気分が反映される。僕は、構図だけを頭に叩き込むようにして順番を待った。でないと壁全体の中での位置関係が分からないまま描くことになってしまう。 5番目ぐらいに呼び出された僕は、進み出る前から、日比野克彦の描いた黄色い鍵穴のかたちにかぶせて、オレンジ色で大きく一筆書きをしてやろうと思っていたので、かなり大きな刷毛を手にした。黄色い丸の中央から右に向かって描き始めた。ほとんどは曲線で、一ヶ所鋭角的なところのあるいつものかたちができあがっているはずだ。確認できないところが致命的だが、最後は左手を置いておいたところに戻って来たので、図としては完結していると思う。 描き終わった頃、町山君がレトララインを持ってきてくれた。彼は、普通小学校に通う全盲の男の子だ。いつも個展のときなど、遠く小田原から見に来てくれる。僕の得意技は、ラインテープで描くことだと知っての援軍だったが、今回は、日比野克彦のワークショップ。与えられた画材でできるだけのことをしてみようと思っていたので、そのテープは使わなかった。 時間の関係もあって、残りの人たちは、10人ずつぐらい同時に前に出て描くことになった。最初、頭の中で整理されていたはずの構図は、僕自身が描いてからは緊張感もなくなり、画面に絵が増えるごとに脳細胞はパニックになっていった。そして、徐々に全体像が思い浮かべられなくなった。たぶん他の視覚障害者もそんな感じだったのではないだろうか。 最後にオプションがあった。ミューズカンパニーの伊地知さんの発案で、壁に描かれた絵を左から順にピアノと、声と、ダンスで即興的に表現しようという試みだ。長年ダンスや音楽のワークショップで培われたノウハウを、一気に公開しようというものらしかった。 僕にはダンスは分からないが、声とピアノのコラボレーションは、なかなかのものだった。それ自体のおもしろさは十分伝わってきた。しかし、その表現が壁に掛かれた絵を伝えるものかどうか、そのあたりはかなり疑問が残った。残念ながら、その即興音楽とともには、僕の頭の中に絵は思い描けなかった。 朝から雷混じりで降り続いていた雨も上がって外に出ると、さわやかな秋の空気が漂っていた。いつの日か、僕の作品を日比野克彦に見せるのだという思いを新たにして新幹線で京都に向かった。 (2000年10月25日) |
| 「阿部こずえさんとの往復書簡その2・ワークショップ編」 この文章は、ワークショップについて、阿部こずえさんとやりとりをした往復書簡です。 阿部こずえさんについては、こちらをご覧ください |
|
阿部)2001年9月21日金曜日 先日の宇都宮美術館のワークショップでは本当に勉強させてもらいました。 予想外の作品がでてきたり、参加者のリアクションが直接伝わってくるというのがおもしろかったです。ワークショップは、単に体験するぐらいにしか考えていませんでしたが、1日じっくりかけて何かがうまれるのを目の当たりにし、しかもその現場を少しでもサポートできたことが、感動的でした。 光島)2001年10月5日金曜日 阿部さんは、ワークショップのアシスタントというのは初めてでしたか? 僕は、ワークショップの講師をさせてもらうようになってもう3年ぐらいになりますね。初めてのワークショップ講師の経験は、当時東北芸術工科大学におられた幸村先生に声を掛けてもらったときです。1998年8月でした。 その頃は、まだ粘土を使ってやってました。 いまから思ってもあれは西村先生の物まねそのものでした。 ふり返るとはずかしいですね。 少しは、西村先生との差別化を図らないとと思ってもがいていましたが、アイマスクをして粘土造形をするという点では全く変わりありませんでしたからね。 参加者は何かを作りたいと思って来ているのに、やたらと僕自身の話ばかりしてい たと思います。 いまのような「触覚絵本作り」というようなスタイルに持ち込んだのはいつからだっ たでしょうか。 このスタイルにもオリジナルというか、盗んできた元になるものがあったんです。 それは、ニール・プライスのワークショップでした。 1997年10月に第2回「地球のみんなのアートフェスタin北九州」というイベントがあってそのとき参加したワークショップなんです。 コピー用紙が閉じられた10ページほどの白紙の本が用意されていました。 それに自分なりの表現で絵本を作っていこうというものです。たしかテーマは、「エッジ(端)」とか、「ルーツ」なんていう哲学的なものでした。 いまのようなスタイルで始めたのは、1999年7月の「エイブル・アート・ワークショップ '99」(スペース アルファ 神戸)からですね。 まだ2年しかたってません。 阿部)10月10日水曜日 こんにちは。阿部です。 往復書簡に入る前に今、目の前にいる友だちが立体コピーを目をとじて、かれこれ15 分は少なくても触り続けている、という中継をします。 彼女は、なにが描かれているか、けっこういいあてています。あってはいないけれど、 この形は、どういう形かということを的確に言っています。ときどき、なぜか歌をうたっている。子供の頃、実家の台所の、ぼこぼこした、文字のような模様のデザインの窓ガラスをよく見ていたなーと思い出して言っています。目をとじて触るというのは、それだけで非日常的経験ですね。 [中継おわり] 往復書簡再開です。 私は、ワークショップの手伝いは他でも経験しているのですが、実は、参加したことというのはほとんどないんですよね。基本的に何かに自ら参加するということはちょっと苦手かもしれません。参加するのに、勇気がいります。光島さんはどうですか。 結構、ワークショップに参加されてますよね。特に最近は美術館などで、ワークショッ プが活発になってきていますね。 光島さんのワークショップでは、触覚絵本を作ってもらって目の見えない光島さんに伝えるという目的ですが、参加者の作品を触るのは、どんな感じですか。触ってどう、というのはわかりませんが、大人でも子供でも「伝えたい」という気持ちが感じとれました。。 光島)2001年12月14日金曜日 僕は、ワークショップの最中に2回参加者の作品を触らせてもらうことにしています。 1度目は、表紙に使う立体コピーの絵に注目しています。そして、どんな雰囲気で制作が進みそうかを伺っています。 ワークショップを始めた頃は、アイマスクをして描くモチーフは、身につけているものとか、すぐ取り出せるものにしていました。ですから、携帯電話やキーホルダー、財布・ペンなどが描かれました。しかし、僕もいつも触っているものであっても、平面 に展開された構図はなかなか認識できませんでした。 10枚中、ヒントなしで分かるのは1、2枚でした。 最近は少し的中率が上がって3、4枚分かるようになってきたようです。こんな風に して、幼児は絵が分かるようになっていくのでしょうか? 携帯なら、アンテナがあり、ボタンが並んでいて、ひものようなものがにょろにょろのびている。目と鼻と口が適当に並んでいれば顔に見えるなんていうことが分かってきました。そんなこと当たり前じゃないかといわれそうですが、頭で分かっていても、実際の図柄として触っていないとピンとこないんですね。 だから、ワークショップを通してずいぶん絵の描き方を勉強していることになります。 あまり人の絵を触っていると自分らしい絵が描けなくなるかもしれないと思うこともあります。 でも、僕が携帯を描くなら、ダイヤルボタンの「5」の位置にあるボツを絶対に描きます。それに、耳を当てるところのスピーカーと声を吸い取るマイクの部分は逃さないと思います。 2度目に触るのは、順番に発表するときです。 ここでは、いかに早く絵を理解するかに賭けています。作者の説明を聞きながら、瞬時に図柄を認識する楽しみですね。かなりうまくできるようになってきたのですが、この間、府中市美術館のワークショップでは、90センチ四方のボードに制作しました。この大きさにはまいりました。 やっぱり画面が大きいとさっぱり分かりません。今の僕の力量だとA4ぐらいが最適ですね。 ただし、画面が大きいと迫力のある作品に仕上がるようなので、それも魅力ですね。 講師の理解不能な作品ができてくることには、喜びも感じます。 というのは、どうしても講師の影響を受けた作品になるというのが、ワークショップの限界でもあるけど、それを越えるようなワークショップでありたいと思っているからです。 ことばになって出てくる、もっと以前のその人自身の内的な個別性の感覚というのがあると思います。そんなものを引き出したいと思っているわけです。 阿部)2002年1月7日月曜日 ワークショップの手伝いをしていて、愉快な瞬間というのが何ケ所かあります。 それは、受講者がアイマスクをとる時です。光島さんの立体コピーの作品「京阪天満橋」の作品をアイマスクをしてさわり、それをとった時のリアクションと、次にやはりアイマスクをして、自分でペンで描いたものを、目でみた時のリアクションです。 両方とも、頭に描いていた図と、実際の作品とのギャップに驚いているのがありありとわかります。また、はじめの驚きに比べ後の方は、多くの人が自分の絵を見て、がっくりした感じが入り交じった驚きになっていたりもする。 さらに私が驚くのは、表紙になる部分が気に入らなかったら、廃材をつかった本づくりの中身の方が続かなくなるのでは、と思うのですが、でもそこから、みんなおもしろいほど、それぞれの作品を仕上げていくのですよね。それがとても不思議です。 ビジュアル的にうまく行かなくても、目が見えない状態で描いている間に、何かがすで に生まれているような気がします。 私は、光島さんが作品づくりをしている時ではなく、ワークショップの講師をしている時に、「鍼灸院の先生」を感じます。うまくいえませんが、「何かを身体の 外にひっぱり出す」感じが。鍼灸師の光島さんを知らないのですが、なんとなくそう思 います。 光島)2002年1月8日火曜日 阿部さんの分析、なかなかおもしろいですね。 僕には参加者の表情が見えないので、想像力で補っている部分をうまく解説してくれましたね。アイマスクを外したときのどよめきを聞きながら、いつも思いをめぐらしていたんです。 それから、「鍼灸院の先生」というのも当たっているかもしれません。ワークショッ プがうまく進んでいると、とってもくつろいで、すがすがしい気分になってくるときがあります。いつもそうだというのではありませんが何度か経験しています。 それは、正月休みなどでしばらく鍼から遠ざかっていて、久しぶりに鍼を持ったときに感じるあのなつかしい感覚とにているのかもしれません。パワーも充実していて患者さんとも適度に距離を保ったいい関係のときです。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||